
僖公二十四年:晋の文公、本国に帰る / 晋の文公制覇の時代

※ 垂耳(文公)が亡命の旅に出て五年目に一度帰国の機会が
訪れた。父の献公が死に、偏愛を受けていた異母弟の奚斉、
卓子が反乱で殺される。やはり、亡命していた異母兄弟の
夷吾(垂耳の母と夷吾の母は姉妹)が祖国に迎えられて即
位、恵公となった。しかし、恵公は、それまで同じ運命に
おかれていた垂耳をよびもどすどころか、かれの存在をお
それて刺客をひける。ために垂耳は、なお流浪の旅をつづ
けなければならなかった。在位十四年で恵公が死に、その
子圉があとをついだ(懐公)。だが、晋の人々は垂耳をし
たうことしきり、ちょうど秦に身をよせていた垂耳のもと
に使者が立ち、秦の穆公の助けによって、重耳は た。懐公
は殺される。【経】 晋侯夷吾(懐公)卒す。
※ 帰 国:僖公二十四年春、王の正月、秦の穆公の力により、
垂耳は晋に帰国、即位した。これを『春秋』に記録してい
ないのは、魯国に通知がなかったからである。その途中、
一行が黄河の岸まで来たとき、随行の子犯は自分があずか
っていた璧(玉の一種、公子の回を垂耳に手渡して、「あ
なたのお供をして、諸国をめぐり歩いて来ましたが、その
間、あなたに対し数えきれぬ無礼をはたらいたことが心に
かかります。あなたにしてみれば、どれほどお腹立ちのこ
とか……。帰国してあなたから罰をうけぬうらに、おいと
まさせていただきます」 垂耳は、「黄河の神に誓って、
わが叔父(子犯は垂耳の叔父にあたる)と仲違いはせぬ」
こう言って誓いを立てると、受けとった璧を黄河の流れに
投げ込んだ。黄河を渡って晋の領域に入ると、垂耳は、ま
ず令孤、ついで桑泉、臼衰と、次々に城をおとして都の絳
(こう)にむかった。
【RE100倶楽部:スマートグリッド篇】

● 「PnP型マイクログリッド」 太陽光に水素・蓄電池を統合
5月31日、イタリアの電力最大手であるエネル(Enel)社は太陽光発電に2種類の蓄電システムを統
合したマイクログリッドが、チリのアントファガスタ(Antofagasta)州で稼働を開始したと発表。
エネルギー貯蔵方法は、❶太陽光の電力で水素を製造して蓄える方法と❷リチウムイオン蓄電池を
併用する。温室効果ガスの排出量がゼロで、設置や撤去、移動などの容易な「プラグ・アンド・プ
レイ(PnP)」型として世界で初めてのマイクログリッドとなる。電力系統に接続する場合と、接
続せずオフグリッドで利用する場合の両方に対応でき、遠隔地や離島など、電化の進んでいない地
域などに有用。太陽光発電の出力は125kW、水素による貯蔵システムの容量は450kWh、蓄電池は
1322kWhの容量である。システム全体の容量が580kWhを超え、さらに太陽光の出力変動を2
つの蓄電システムで平準化できるので、安定した出力を供給するエネルギー源として運用できる。
マイクログリッドとしての柔軟性や安定性を確保する。チリ北部にあるアントファガスタ州のオヤ
ーグ(Ollagüe)に建設し、同社の「Cerro Pabellón」地熱発電所で勤務する約6百人の作業員宿舎の
電力の一部を賄う。再生可能エネルギー事業をチリで行うために設立したグループ会社、エネル・
グリーン・パワー・チリ(EGPC)社を通し進める。
エネル社は、設備容量ベースでチリ最大の再エネ事業者という。同社が運用する再エネ電源は、風
力564MW、太陽光492MW、水力92MWで、これらの合計は1.1GWを超える。48MWのCerro
Pabellón 地熱発電所も運転を開始したばかり。Cerro Pabellónは南米では初めての地熱発電所(海抜
4500mという高度の高い場所)。建設された商用の地熱発電所も世界初である。エネルは傘下
の再エネ発電事業者であるエネル・グリーン・パワー社を通じてグローバルでプロジェクト開発に
取り組んでいる。チリでは、2016年6月に同国最大となる160MWのメガソーラー(大規模太陽光
発電所)「Finis Terrae」が稼働中。南米ではチリ以外に、メキシコ、ペルー、ブラジルなどでも風
力や太陽光のプロジェクトを開発しているが、このまま行けば、わたし(たち)が提唱する「エネ
ルギーフリー社会」をもっとも早く実現する国となるかもしれない。しかも、日本と同様にチリは
地震国で、商用原発はゼロ(研究炉2基が存在する)。 June 1, 2017
June 1, 2017
【RE100倶楽部:スマートグリッド篇】
● 3との精密林業技術でバイオマス供給増産
再エネのなかで、原理的/技術的な側面から評価すると、風力/太陽光発電のエネルギー理論変換限
界効率の技術はほぼ達成/あるいは到達のための開発目標/工程表が明確にされているなか、バイオ
マスのそれは明らかででなかった。今月1日、NEDOのプロジェクトで日本製紙(東京都公社)、東
京農工大学(東京都府中市)、千葉大学(千葉県千葉市)は、❶林業用土壌センシング技術、❷DNA
マーカー育種技術と❸リモートセンシング技術の3つを活用し、植林木の単位面積あたりのバイオマ
ス生産量を現行法の1.8倍以上に増やせる精密林業技術を開発したこと発表。
同技術は、NEDOのプロジェクトにおいて、2013年12月から2017年2月までの約3年間、ブラジル北部
にある日本製紙保有のユーカリ植林地で品種改良、植栽技術向上等によるバイオマスの収量アップを
目的に進めてきた委託研究で開発。ところで、バイオ燃料は、化石燃料に対して競争力を持つため原
材料の低コスト化が求められ、植林地の単位面積あたりから得られるバイオマス生産量が課題になる。
また、安価で高品質な植林木の供給は、天然林の伐採量を緩和できるため、地球環境の保全にも役立
つ。日本製紙は、今回の成果を海外植林地の木質バイオマスの生産に活用し、林業のほか木質バイオ
マスを主要原料とする幅広い製造業の発展・強化を目指すとのこと。このように、量産/品質/収量
の安定化の目途がたっことになった。今後は、バイオマスのエネルギー変換効率や加工プロセスの効
率化/加工プロセス多様化が残件が焦点となる。これで風力×太陽光×バイオマス×水力×(地熱)
の4(5)つがそろい踏みし夢が実現することになる。 June 1, 2017
June 1, 2017
1.新たな技術でユーカリチップ原材料費は44%削減
❶ 林業用トラクタ搭載型土壌センシング装置
林業用土壌センシング技術として、植林地ほ場において、栄養成分などの土壌情報を効率的かつ迅速
に収集できる、林業用のトラクタ搭載型土壌センシング装置(土壌センサー)を開発した。これを用
いて、土壌を迅速に評価することにより、植林木の成長に適した土地が選択でき、現行法と比較して
1.3倍のバイオマス生産量の確保が可能になる。
❷ 有用形質を間接選抜するDNAマーカー育種技術
DNAマーカー育種技術は、植林木がもつゲノム(DNAの塩基配列の違い)を目印(DNAマーカー)
に、成長性や、体積当たりの重さ(容積重)、セルロース量、パルプ収率など木質特性等の有用形質
を間接的に選抜するもの。この技術により、推定バイオマス生産量が現行の1.4倍以上となる優良
木の選抜にも成功した。これら2つの技術を合わせると、単位面積当たりのバイオマス生産量が現行
法と比べて1.8倍以上(1.3×1.4)に増やすことが可能で、ユーカリチップ原材料費(立木費、
伐採費、輸送費、切削費)を44%削減することが期待できる。

➌ 高精度なバイオマス量評価を行うリモートセンシング技術
リモートセンシング技術は、ドローン(自律飛行可能な無人航空機)、3Dレーザースキャナ(レーザ
ーを用いて3次元構造物を計測する装置)を使用した、広大な植林地における高精度なバイオマス量評
価のための技術で、バイオマス量をより精密で高効率に測定することが可能となった。


読書録:村上春樹著『騎士団長殺し 第Ⅱ部 遷ろうメタファー編』
34.そういえば最近、空気圧を測ったことがなかった
時計は午後二時を少しまわっていた。ひどくくたびれたという感覚があった。私はクローゼッ
味噌汁をつくった。そしてそれを一人で黙って食べた。語りかけるべき相手心いないし、語るべ
き言葉も見当たらない。その簡素なひとりぼっちの夕食を食べ終えかけた頃に、玄関のベルが鳴
った。どうやら私かあと少しで食事を終えようというところで玄関のベルを鳴らそうと、人々は
心を決めているらしかった。
一日はまだ終わってはいなかったのだ、と私は思った。長い日曜日になりそうな予感がした。
私はテーブルの前から立ち上がり、ゆっくりと玄関に向かった。
35.あの場所はそのままにしておく方がよかった
私はゆっくりとした足取りで玄関に向かった。玄関のベルを鳴らしているのが誰なのかまった
く見当がつかなかった。もし車が家の前に停まれば、その音は聞こえたはずだ。食堂は少し奥ま
ったところにあるが、とても静かな夜だったし、車がやってくればそのエンジン音やタイヤの軋
みは必ず耳に届くはずだ。たとえそれがもの静かなハイブリッド・エンジンを誇るトヨタ・プリ
ウスであったとしてもだ。しかしそんな音はまったく聞こえなかった。
そして日が落ちてから、車を使わずにここまで長い坂道を歩いて登ってくるような物好きな人
間はまずいない。照明もほとんどなく道はずいぶん暗いし、人気もない。孤立した山の上にぽつ
んと建った家なので、近くには隣人と呼べるような人々もいない。
ひょっとしたら騎士団長かもしれないと私は思った。しかしどう考えても彼であるわけはない。
今ではもう、好きなときに好きなだけこの家に入ってくることができるのだから、わざわざ玄関
のベルを押したりはしない。

相手が誰かを確かめもせずにロックを外し、玄関のドアを開けた。そこには秋川まりえが立っ
ていた。昼間とまったく同じかっこうだったが、今はョットパーカの上に紺色の薄手のダウン・
ジャケットを着ていた。日が落ちてさすがにあたりは冷え込んでいた。そしてクリーブランド・
インディアンズの野球帽をがぶり(どうしてクリーブランドなのだろう?)、右手に大きな懐中
電灯を持っていた。
「入ってかまわない?」と彼女は尋ねた。〈こんばんは〉もなければ、〈突然うかがってごめん
なさい〉もなかった。
「かまわないよ、もちろん」と私は言った。それ以上のことは何も言わなかった。私の頭の中の
抽斗はまだうまくきちんと閉まっていなかったからだ。まだ奥の方に毛糸の玉がつっかえている。
私は彼女を食堂に案内した。
「食事の途中なんだ。最後まで食べちやっていいかな?」と私は言った。
彼女は黙って肯いた。社交性といった面倒な概念は、この少女の頭の中には存在しないのだ。
「お茶を飲む?」と私は尋ねた。
彼女はやはり黙って肯いた。そしてダウン・ジャケットを脱ぎ、野球帽をとって髪を整えた。
私はやかんでお湯を沸かした。そして急須に緑茶の葉を入れた。どうせ私もお茶を飲みたかった
ところだ。
私がブリの粕漬けを食べ、味噌汁を飲み、米飯を食べるのを、秋川まりえはテーブルに肘をつ
いて、珍しいものでも見るように見ていた。まるでジャングルを散歩している途中、巨大ニシキ
ヘビが穴熊の子供を呑み込む現場に出くわして、近くの石の上に腰を下ろしてそれを見物してい
るみたいに。
「ブリの粕漬けは自分で作ったんだ」、深まっていく沈黙を埋めるために私は説明した。「こう
しておけば日待ちがするから」
彼女は何の反応も示さなかった。私の言葉が耳に入っているのかどうかさえ確かではなかった。
「イマヌエル・カントはきわめて規則正しい生活習慣を待った人たった。町の人々は彼が散歩を
する姿を見て、それに時計の時刻を合わせたくらいだ」と私は言ってみた。
もちろん意味のない発言だ。秋川まりえが意味のない発言に対してどんな反応をするか、様子
を見てみたかっただけだ。私の言ったことが本当に耳に届いているのかどうか。しかし彼女はま
ったくどのような反応も示さなかった。あたりの沈黙がより深まっただけだった。イマヌエル・
カントはあくまで日々寡黙に規則正しく、ケーニヒスベルクの通りから通りへと散策を続けてい
た。彼の人生最後の言葉は「これでよし(Es ist gut)」だった。そういう人生もあるのだ。
私は食事を終え、使った食器を流し台まで運んだ。それからお茶をいれた。二つの湯飲みを待
ってテーブルに戻った。秋川まりえはテーブルの前に座ったまま、私のひとつひとつの動作をじ
っと眺めていた。文献の細かい脚注を検証する歴史学者のような注意深い目で。
「車でここまで来たわけじゃないよね?」と私は尋ねた。
「歩いてきた」と秋川まりえはようやく口を開いた。
「君のうちからここまで一人で歩いてきた?」
「そう」
私は黙って相手の話の続きを待った。秋川まりえも黙っていた。食堂のテーブルを挟んで、二
人のあいだにかなり長く沈黙が続いた。しかし沈黙を維持することにかけては、私も決して不得
意な方ではない。何しろ山のてっぺんでずっと一人で暮らしているくらいだ。
「秘密の通路があるの」とまりえはしばらくあとで言った。「車で来るとけっこう道のりは長い
けれど、そこを抜けてくるととても近い」
「しかしぼくもずいぶんこのあたりを散歩しているけれど、そんな道を目にしたことはないよ」
「探し方が悪いから」とその少女はあっさりと言った。「普通に歩いて普通に見ていたのでは、
通路は見つからない。うまく隠してあるから」
「君が隠したんだね?」
彼女は肯いた。「私は生まれてすぐここに来て、ここで育ったの。小さい頃から山ぜんたいが
私の遊び場だった。このへんのことは隅から隅まで知っている」
「そしてその通路は巧妙に隠されている」
彼女はもうコ伎こっくりと肯いた。
「そして君はその通路を辿ってここにやってきた」
「そう」
私はため息をついた。「食事はもう済んだの?」
「さっき終わった」
「どんなものを食べた?」
「叔母さんはあまり料理が得意ではない」と少女は言った。私の質問に対する答えにはなってい
ないが、それ以上はあえて追及しなかった。白分かさっき食べたもののことをきっとあまり思い
出したくないのだろう。
「それで君の叔母さんは、君が一人でここに来ていることは知っているのかな?」
まりえはそれには返事をしなかった。唇をまっすぐ堅く結んでいた。だから私が自分で返事を
することにした。
「もちろん知らない。まともな大人は十三歳の女の子に、暗くなってから一人で山の中をうろつ
かせたり はしない。そうだよね?」
またひとしきり沈黙が続いた。
「秘密の通路があることも彼女は知らない」
まりえは首を何度か横に振った。叔母は通路のことは知らないという意味だ。
「君以外にその通路のことを知っている人はいない」
まりえは首を何度か縦に振った。
「いずれにせよ」と私は言った。「君のおうちのある方角からすると、君はきっと通路を抜けた
あと、古い祠のある雑木林を通ってここに来たんだろうね?」
まりえは肯いた。「祠のことはよく知っている。このおいた、大きな機械を使ってその裏手に
ある石の塚を掘り返したことも知っている」
「君はその現場を見ていたの?」
まりえは首を振った。「掘り起こしたところは見ていない。その日は学校に行っていたから。
見たときには機械のあとが地面にいっぱい残っていた。どうしてそんなことをしたの?」
「いろんな事情があったんだ」
「どんな事情?」
「最初から説明すると、けっこう長い話になってしまう」と私は言った。そして説明はしなかっ
た。そこに免色が関与していることを、できることなら私は彼女に教えたくなかった。
「あそこはあんな風に掘り起こしたりするべきではなかった」、まりえは唐突にそう言った。
「どうしてそう思うの?」
彼女は肩をすくめるような動作をした。「あの場所はそのままにそっとしておく方がよかった。
みんなそうしてきたのだから」
「みんなそうしてきた?」
「長いあいだずっと、あそこはそのままにされてきたのだから」
たしかにこの少女の言うとおりかもしれない、と私は思った。あの場所には手をつけるべきで
はなかったのかもしれない。これまでみんながそうしてきたのかもしれな
い。しかし今になってそんなことを言っても手遅れだ。石の塚は既にどかされ、穴はあばかれ、
騎士団長は解放されてしまったのだ。
「あの穴にかぶせておいた蓋を取ったのはひょっとして君だったのかな?」と私はまりえに尋ね
た。「穴の中をのぞき、それからまた蓋をして、石の重しを元通りに載せておいた。そうじやな
いか?」
まりえは顔をあげて私の顔をまっすぐ見た。なぜそれがわかるの、というように。
「蓋の上の石の並べ方が少しだけ違っていたから。ぼくは視覚的な記憶力が昔からとてもいいん
だ。そういうちょっとした違いが一目でわかる」
「ふうん」と彼女は感心したように言った。
「でも蓋を開けても穴の中はからっぽだった。暗闇と湿った空気以外には何もなかった。そうだ
ね?」
「梯子がひとつ立てかけてあった」
「穴の中には降りてないよね?」
まりえは強く首を振った。まさかそんなことをするわけはない、というように。
「それで」と私は言った。「君は今夜こんな時刻に、何か用件があってここまで来たんだろう
か? それともただの社交的訪問なのかな?」
「社交的訪問?」
「たまたま近所まで来たから、ちょっと挨拶に寄ってみたとか?」
それについて彼女は少し考えた。それから首を小さく振った。「社交的訪問というのでもない」
「だとしたら、これはどういう種類の訪問なんだろう?」と私は言った。「もちろん君がうちに
遊びに来てくれるのは、ぼくとしても嬉しいけれど、もしあとで君の叔母さんやお父さんにこの
ことがわかったら、妙な誤解を受けることになるかもしれない」
「どんな誤解?」
「世間にはあらゆる種類の誤解がある」と私は言った。「ぼくらの想像を遥かに超えたような誤
解もある。ひょっとしたらもう君をモデルにして絵を描くことを許可されなくなるかもしれない。
それはぼくとしてはすごく困ることなんだ。君にとっても困ることじやないかな?」
「叔母さんにはばれない」とまりえはきっぱりと言った。「夕食が終わったら、わたしは自分の
部屋に引きあげるし、そのあと叔母さんはわたしの部屋にはやってこないから。そういう取り決
めになっている。だから窓からこっそり抜け出してもだれにもわからない。一度だってばれたこ
とはない」
「昔からよく夜の山の中を歩きまわっていた?」
まりえは肯いた。
「夜の山の中に一人でいて怖くないの?」
「もっと怖いものはほかにある」
「たとえば?」
まりえは小さく肩をすぼめるような動作をしただけで、返事はしなかった。
私は尋ねた。「叔母さんはともかく、お父さんはどうしているの?」
「まだ家に帰っていない」
「日曜日なのに?」
まりえは返事をしなかった。父親のことにはなるべく触れたくないようだった。
彼女は言った。「とにかく先生は心配しなくていい。わたしが一人で外に出ていることはだれ
にもわからないから。そしてもしわかったとしても、先生の名前はぜったいに出さない」
「じやあ、もうその心配はしない」と私は言った。「しかし、今夜どうしてわざわざ君はぼくの
うちにやって来たのだろう?」
「先生に話があったから」
「どんな話?」
秋川まりえは湯飲みを手に取り、熱い緑茶を一ロ静かに飲んで、それから鋭い目で周囲をぐる
りと見回した。話を聞いているものがほかにいないことを確かめるように。もちろんまわりには
我々のほかには誰もいない。もし騎士団長が戻ってきて、どこかで耳を澄ませていなければの話
だが。私もあたりを見回してみた。しかし騎士団長の姿は見えなかった。とはいえ、騎士団長が
形体化していなければ、誰の目にもその姿は見えないわけだが。
「今日のお昼にここに来た、あの先生のお友だちのこと」と彼女は言った。「きれいなしらがの
ひと。なんていう名前だったっけ。ちょっと珍しい名前」
「免色さん」
「そうメンシキさん」
「彼はぼくの友だちじやない。少し前に知り合っただけの人だよ」
「なんでも」とまりえは言った。
「で、免色さんがどうかしたの?」
彼女は目を細めて私を見た。そして少しだけ声をひそめて言った。「あの人はたぶんなにかを
心に隠していると思う」
「たとえばどんなことを?」
「そこまではわからない。でもメンシキさんが今日の午後、ただ偶然立ち寄ったというのは、た
ぶんホントじゃないと思う。きちんとしたなにかがあってここに来たんだという気がする」
「何かって、たとえばどんなことなんだろう?」、私は彼女の観察眼の鋭さにいくぶんひるみな
がらそう尋ねた。
この講つづく
● 疾走するロードスター:近江八幡国民休暇村
晴天といえど、PM2.5濃度が30PPMを超しているのか曇天で霞むなか車を走らせ近江八幡の国
民休暇村にさしかかると彦根市の中学一年生たちが手作りボートレース中。早速デジカメ、良い体
験になるねとはなしながら、水ケ浜のシャレーに向かう。到着すると看板の取り付け作業中、むべ
が枯れていたのに驚き彼女が作業中のマスターに理由を訊いている。食事を済ませ暫く休息し正午
過ぎ帰宅。好日とまで言えぬが、たまのドライブでリフレッシュ。





































































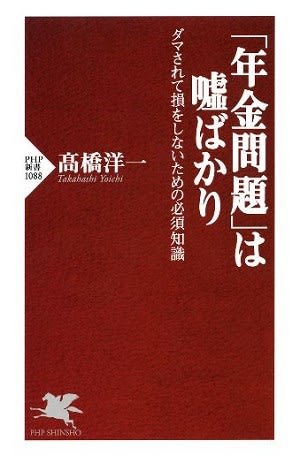





















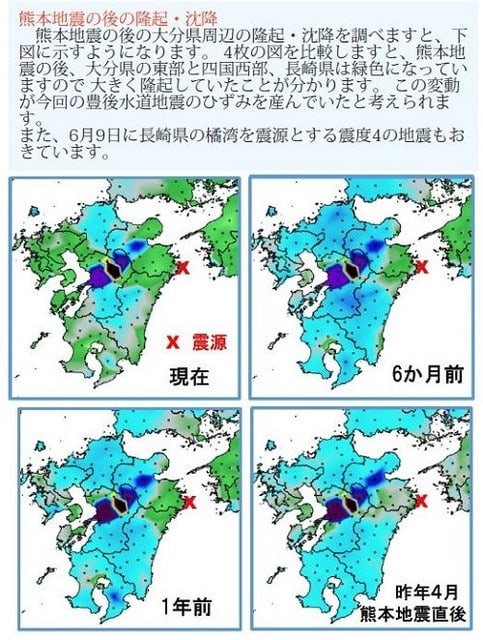
























































 July 2, 2017
July 2, 2017











 年金から天引きされる所得税・住民税以外の特別税の根拠は?
年金から天引きされる所得税・住民税以外の特別税の根拠は?
