
 やっぱり日本製の列車はいい。揺れないし安全ね。
やっぱり日本製の列車はいい。揺れないし安全ね。
ミヤンマーの 「あまちゃん列車」
● 天をみくびるな
公孟子が墨子にいった。
「人が行動するさい、義か不義かということが問題です。吉か凶かなどということは論ずる必要はな
い」
「それはちがう。むかしの聖王は鬼神が確かに存在し、人の行為を判断して禍福をくだすと考えた。
聖王の時代に国が立派に治まったのは、かれらが天の賞罰を信じて国を治めたからだ。
だが、桀王や紂王などは、そうは考えなかった。鬼神には人の行為を判断する力はなく、禍福をく
だすことなどできないと考えた。かれらの時代に国が賊びたのは、かれらが天の賞罰を信じないで、
国を冶めたからだ。
先王の書には、『人が倣るのは、天をみくびるからだ』という箕子のことばがつたわっている。こ
れは不義をなす者には罰がくだり、善をなす者には賞が与えられることを意味している」
※ 天の声
鬼神の存在をみとめることを今日の感覚で。"迷信"と決めつけることは容易である。が、慎みの心は、人
間の自信過多症に対する処処方箋として、時代の差を超越しているのではなかろうかと解説されるが、哲
学や複雑系経済学上の「因果報応」「因果律」という言葉に当り、「天の声」は慎み深く洞察するものし
か聞くことができないと諭すものであろう。
【抗癌最終戦観戦記 Ⅳ】
● 前立腺がん治療に光 抗がん剤、肝炎薬で効果復活
前立腺がんの抗がん剤が効かなくなった患者に既存の抗ウイルス薬を併用すると、再び効果が得られる可能性が
あるとの研究結果を、慶応大などのグループがまとめた。来春から医師主導の治験を始める計画。京都市で開か
れている日本癌(がん)治療学会で30日、発表。
慶応義塾大学医学部の大家基嗣教授らの研究グループは、抗がん剤が効かなくなったがんに対し、別の薬
剤の投与で再び抗がん剤が効くようにする新しい治療法の臨床試験に成功。抗がん剤「ドセタキセル」が
効かなくなった進行性の前立腺がんの患者に対して抗肝炎ウイルス薬「リバビリン」を併用し、5例中2
例で、前立腺がんのバイオマーカー(目印となる生体物質)の値が下がることを確認。現在、ドセタキセ
ルが効かなくなった前立腺がんに対する有効な治療法がなく、新たな治療法として期待でき、16年3月
をめどに慶大病院で医師主導型の治験を始める。同研究チームは、ドセタキセルが効きにくいがん細胞を
持つマウスに、ドセタキセルとリバビリンを投与することで治療の有効性を確認していたが、抗がん剤が
効かなくなるよう変化したがん細胞中の遺伝子の性質を、再び効くようにリバビリンが変化させる作用メ
カニズムが考えられるという。
これをみて、理解できたる人はどれほどいるのだろうと考え込む。「ガン細胞の生理特性を利用し、2種
類の抗ガン剤を投薬タイミングを変えて投与し治療する方法」ということの他になにがあるのか、マイク
ロ(ナノ)カプセル技術などによる同時投与ではだめなのかと。まず用語が複雑である。(1)リバビリ
ン:日常臨床において広く使用され、ヒトに対する安全性が既に確立されている抗ウイルス薬。13年に
泌尿器科学教室において、病理学教室、発生・分化生物学教室ならびに産業総合研究所との共同研究によ
り、ドセタキセル療法が効きにくい患者に対し有用な可能性が高い薬剤として世界で初めて発見し報告
(Kosaka T et.a1 CancerScience 2013/下図クリック)。この発見には、難洽既がんの治療に発生学・幹
細胞医学の手法を取り入れ、生物情報工学による遺伝子発現プロファイルの解析を融合し、効果的な薬剤
を抽出していくという。(2)リプログラミング療法:山中教授によるiPS細胞誘導に代表されるように、
分化した細胞をリセットして受精卵のような発生初期の未分化な状態に巻き戻すことを、最近ではリブロ
グラミング・再プログラム化・初期化と表現されることが多いが、今回、本研究グループは、抗がん剤が
効きにくくなったがんを抗がん剤が効くようにするという治療法が、抗がん剤の感受性を巻き戻すという
点において、リプログラミングするという概念と近似していることから、リブログラミング療法と提唱し
ている。(3)ホルモン療法:省略、(4)癌幹細胞:省略、(5)遺伝子発現プロファイル:省略、
(6)遺伝子発現プロファイル:省略、(7)ドラッグリポジシッニング:特定の疾患に有効な治療薬か
ら、別の疾患に有効な新たな薬効を見いだすという新薬開発の方法。
この領域については、残件扱いとして、いずれまとめて考察する。

● 折々の読書 『職業としての小説家』 27
小説を書いていて、いちばん楽しいと僕が感じることのひとつは、「なろうと思えば、自分は
誰にでもなれるんだ」ということです。
僕はもともと一人称「僕」で小説を書き始め、そういう書き方を二十年くらい続けました。短
編なんかではときどき三人称を使いましたが、長編に関していえばずっと丁人称「僕」でとおし
てきました。もちろん僕=村上春樹ではなく(レイモンド・チャソドラー=フィリップ・マーロ
ウではないのと同じように)、それぞれの小説によって「僕」の人物像は変わってくるわけです
が、それでも一人称で書き続けていると、現実の僕と、小説の主人公の「僕」の境界線が時とし
て――書き手にとっても、また読み手にとっても――ある程度不明瞭になるのはやむを得ないこ
とです。

最初のうちはそれでも問題はなかったのだけど、というか僕自身、架空の「僕」を挺子の支点
にして小説世界を立ち上げ、広げていくことをひとつの目的としていたのですが、そのうちにだ
んだんそれだけでは間に合わないと感じるようになってきました。とくに小説が長く大きくなる
につれて、「僕」という人称だけではいくぶん狭苦しく、息苦しく感じるようになってきました。
『世界の終りとハードボイルド・ワソダーランド』では、「僕」と「私」という二種類の一人称を
章ごとに使い分けていますが、それも一人称の機能の限界を打開しようという試みのひとつだと
思います。

一人称だけを用いて書いた長編小説は、『ねじまき鳥クロニクル』(一九九四・九五)が最後の
ものになります。しかしこれだけ長くなると、「僕」の視点で語られる話だけではおっつかなく
て、あちこちに様々な小説的工夫が持ち込まれています。他の人の語りを入れるとか、長い書簡
をもってくるとか……とにかくありとあらゆる話法のテクニックを導入して、一人称の構造的制
限を突き破ろうとしています。しかしさすがに「これがもう限界だな」と感じるところがあり、
その次の『海辺のカフカ』(二〇〇二)では半分だけを三人称の語りに切り替えています。カフ
カ少年の章はこれまでどおり「僕」が語り手になって話が進みますが、それ以外の章は三人称で
語られています。折衷的と言えばそのとおりなんですが、たとえ半分であるにせよ三人称という
ヴォイスを導入することによって、小説世界の幅を広げることができた――と僕は思っています。
少なくとも僕自身はこの小説を書きながら、『ねじまき鳥クロニクル』のときよりは、手法的な
レベルで自分がずっと自由になっていると感じました。

そのあとに書いた短編小説集『東京奇譚集』、中編小説『アフターダーク』はどちらも、最初
から最後まで純粋な三人称小説になっています。僕はそこで、つまり短編小説と中編小説という
フォーマットで、自分に三人称がしっかり使えることを確かめているみたいです。買ったばかり
のスポーツカーを山道に持っていって試し乗りし、いろんな機能のフィールを確かめるみたいに。
そういう流れを順番に追ってみると、僕が一人称に別離を告げ、三人称だけを使って小説が書け
るようになるまでに、デビュー以来ほぼ二十年を要していることになります。ずいぶん長い歳月
ですね。
人称の切り替えにどうしてそれほど長い時間が必要だったのか? その正確な理由は自分でも
よくわかりません。ただ何はともあれ、「僕」という一人称を使って小説を書く作業に、僕の身
体と精神がすっかり馴れてしまっていたということなのでしょう。だからその転換に時間がかか
ったのだと思います。それは僕にとってはただの人称の変化というより、大げさに言えば視座の
根本的な変更に近いことだったのかもしれません。

僕は何ごとによらず、ものごとの進め方を切り替えるのに時間がかかる性格みたいです。たと
えば、登場人物に名前を与えることが長いあいだできませんでした。「鼠」とか「ジェイ」とか、
そういう呼び名みたいなものはまあオーケーだったんですが、きちんとした姓名がどうしてもつ
けられませんでした。どうしてか? そう質問されても自分でもよくわかりません。「ただ人に
名前をつけるのが、どうにも恥ずかしかったから」としか言えません。うまく言えないんだけど、
僕みたいな者が勝手に人に(たとえそれが自分でこしらえた架空の人物であれ)名前を賦与する
なんて、「なんか嘘っぽい」という気がしたんです。最初のうちは小説を書くという行為自体が、
僕にとって何かしら恥ずかしかったということもあるかもしれません。小説を書いていると、ま
るで自分の心を裸で人前に放り出しているみたいで、ずいぶん恥ずかしかったのです。
主要人物になんとか姓名がつけられるようになったのは、作品で言えば『ノルウェイの森』
(一九八七)からですね。つまりそれまでの最初の八年くらいは、基本的に名前を持だない登場
人物を用いて、一人称で小説を書いてきたわけです。考えてみれば、ずいぶん不自由なこと、ま
わりくどい制度を自らに押しつけて小説を書いてきたわけですが、そのときはそれほど気になら
なかった。まあこういうもんだろう、と思ってやっていました。
でも小説が長く複雑になるにつれて、そこに登場する人々が名前を持たないことに、僕もさす
がに不自由を感じるようになりました。登場人物の数が増えれば、そして彼らが名前を持だなけ
れば、当然そこに具体的な混乱が生じてきます。だからあきらめて腹をくくり、『ノルウェイの
森』を書くときに「名前付け」を断行しました。簡単ではありませんでしたが、目をつぶって
「えいやっ」とやってしまうと、その後は登場人物に名前をつけるのは、さして難行ではなくな
りました。今ではとくに苦労もなく、さらさらと適当な名前をつけています。『色彩を持だない
多崎つくると、彼の巡礼の年』のように、主人公の名前がタイトルになる本まで書くようになり
ました。『1Q84』も女主人公に「青豆」という名前がついた時点で、話は勢いを得て前に進
み出しました。そういう意味では名前というのは、小説にとってとても重要な要素になります。
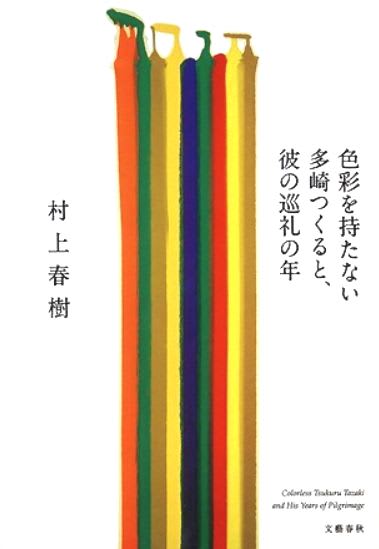
このように僕は、新しい小説を書くたびに、「よし、今回はこういうことに挑戦してみよう」
という具体的な目標――その多くは技術的な、目で見える目標です-をひとつかふたつ設定す
るようにしています。僕はそういう書き方をするのが好きなのです。新しい課題をクリアし、今
までできなかったことができるようになることで、白分か少しずつでも作家として成長している
という具体的な実感が得られます。一段一段梯子を登っていくみたいに。小説家の素晴らしいと
ころは、たとえ五十歳になっても、六十歳になっても、そういう発展・革新が可能であるという
ことです。年齢的な制限というのがあまりありません。スポーツ選手なんかだとなかなかそうは
いかないでしょう。
小説が三人称になり、登場人物の数が増え、彼らがそれぞれに名前を得たことによって、物語
の可能性が膨らんでいきました。つまりいろんな種類の、いろんな色合いの、いろんな意見や世
界観を持った人物を登場させられるし、そういう人たちの多種多様な絡み具合を描いていけるよ
うになりました。そして何より素晴らしいのは、自分が「ほとんど誰にでもなれる」ということ
でした。一人称で書いていたときにも、その「ほとんど誰にでもなれる」という感覚はあったの
ですが、三人称になるとその選択肢が更にぐっと広がります。
一人称小説を書くとき、その多くの場合、僕は主人公の(あるいは語り手の)「僕」を〈広義
の可能性としての自分〉として大まかに捉えているのだと思います。それは〈実際の僕〉ではな
いけれど、場所や時間を変えられていたら、ひょっとしてこうなっていたかもしれない自分の姿
であるわけです。そのような形で枝分かれさせていくことで、僕は自己を分割していた、という
ことになるかもしれません。そして自己を分割し、物語性の中に放り込むことで、自分という人
間を検証し、自分と他者との――あるいは世界との接面を確かめていたわけです。最初の頃の僕
にはそういう書き方が合っていました。そして僕が愛好する小説の多くも、一人称で書かれてい
ました。

たとえばフィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』も一人称の小説です。小説の主人公
はジェイ・ギャツビーですが、語り手はあくまでニック・キャラウェイという青年です。私(ニ
ック)とギャツビーの接面の微妙な、しかしドラマチ″クな移動を通して、フィッツジェラルド
は自己の有り様を語っています。そういう視点が物語に深みを与えています。
しかし物語がニ″クの視点で語られることは、小説が現実的な制約を受けることをも意味しま
す。ニックの目が届かないところで何かが起こっても、それを物語に反映することがむずかしい
からです。フィッツジェラルドはいろんな手法を用いて、小説的テクニックを総動員して、その
制約を巧妙にクリアしていきます。それはそれでもちろんとても面白いんですが、そういう技術
的工夫にもおのずと限界はあります。事実、その後フィッツジェラルドは『グレート・ギャツビ
ー』のような構成の長編小説は書いていません。
サリンジャーの『キャッチャー・イン・ザ・ライ』もとても巧妙に書かれた、優れた一人称小
説ですが、彼もその後、同じような書き方をした長編小説は発表していません。たぶんその構成
上の制約のために、小説の書き方が「同工異曲」になることを恐れたためではないかと僕は推測
します。そしてたぶん彼らのそのような判断は正しかったはずです。
たとえばレイモンド・チャンドラーのマーロウもののような「シリーズ小説」であると、そう
いう制約のもたらす「狭さ」が遂に有効な親密なルーティーンになって、うまく機能を発揮する
わけですが(僕の場合、初期の「鼠」ものにはそういうところが少しくらいあるかもしれません)、
単発ものの場合、丁人称の持つ制約の壁は、書き手にとってだんだん息苦しいものになっていく
ことが多いようです。だからこそ僕も一人称小説という形式に対して、いろんな方向から揺さぶ
りをかけ、新しい領域を切り拓こうと努めてきたわけですが、『ねじまき鳥クロニクル』に至っ
て「これがそろそろ限界だ」と痛感しました。
『海辺のカフカ』で半分に三人称を導入して、いちばんほっとしたのは、主人公のカフカくん
の物語と並行して、中田さん(不思議な老人)と星野さん(いささか粗暴なトラック運転手)の
物語を進めて行けたことです。そうすることによって僕は、自己を分割するのと同時に、自己を
他者に投影できるようにもなったわけです。より正確に言うなら、分割した自己を他者に託する
ことができるようになったということです。そしてそうすることによって、コンビネーションの
可能性が大きく広がりました。そして物語も複合的に技分かれし、いろんな方向に広がっていけ
るようになりました。
だったらもっと前に三人称に切り替えておけばよかったじやないか、そうすればもっと進歩も
早かっただろうに、と言われそうですが、実際にはなかなかそう簡単にいきません。性格的に融
通があまりきかないということもありますが、小説的視座を切り替えるとなると、小説の構造そ
のものに大きく手を入れることになりますし、その変革を支えるための確かな小説的技術と基礎
体力が必要になります。だからこそ少しずつ様子を見ながら、段階的にしかそれができなかった
ということもあるでしょう。身体で言えば、運動目的にあわせて骨格と筋肉を少しずつ改造して
いかなくてはならなかったということです。肉体改造――それには手間と時間がかかります。
「第九回 どんな人物を登場させようか?」
村上春樹 『職業としての小説家』
本を読んでいると、トルコでは新婚のとき新郎がザクロを地面に投げて割り、飛散した種子の数で、その
夫婦のあいだに生まれる子どもの数を占ったという習わしをイメージした。なぜか?小説の創作過程の産
みの苦しみと喜びを連想したため。
この項つづく




