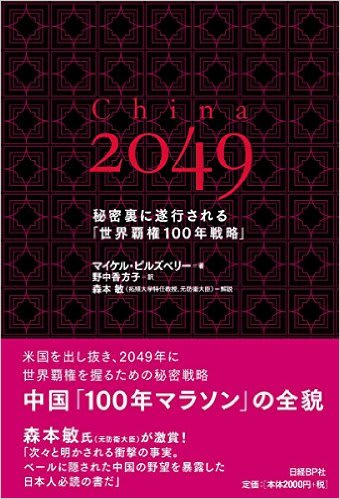動物一般の社会はほとんど意図的な生産をやらないで消費行動だけをやって、
あとに残余として昨日とおなじ身体状態をのこす。
意図的な高度な生産をあたかも生産がほとんど行われていないかのように考察
の彼方へ押しやり、消費行動だけが目に立つ重要な行為であるかのようにあつ
かおうとしている。
これはラセン状に循環して次元のちがったところで動物一般の社会に復帰して
いるような画像にみえてくる。
相違はわたしたちのなかにメタフィジックが存在するということだけだ。この
メタフィジックによれば消費は遅延された生産そのものであり、生産と消費と
は区別されえないということになる。
「《ハイ・イメージ論》消費論(2)」海燕 1990.6.1
※ キーワード:消費社会/第三次産業化/価値の高次化/企業系列の網状化

Takaaki Yoshimoto 25 Nov, 1924 - 16 Mar, 2012
● 百名山踏破:木曽駒ヶ岳を追加計画
昨日に続いて、複数選択肢を準備する(理由:うかうかすると1座も踏破できない可能性があり、
チャンスがあればすぐに実行するため)。今回は中央アルプス木曽駒ヶ岳。

長野県の南部に位置する山。木曽山脈の主峰である木曽駒ヶ岳は、標高 2,612メートルの千畳
敷までバスとロープウェイを利用して登ることができ、登山者とともに多くの行楽客が訪れる。従
って、ロープウェイを利用すれば4~5時間のピストン行程で踏破できるのでややこしいなら日帰
りコースも有力な選択肢だ。
さて、木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ)は長野県上松町・木曽町・宮田村の境界に聳える。木曽山脈
(中央アルプス)の最高峰。日本百名山、新日本百名山、花の百名山に選定。木曽駒と呼ばれるこ
ともある。駒ヶ岳の名を冠する山は日本の全国に多数あり、その最高峰である南アルプスの甲斐駒
ヶ岳とこの木曽駒ヶ岳に挟まれる伊那谷では、この山を西駒ヶ岳または西駒、甲斐駒ヶ岳を東駒ヶ
岳または東駒と呼ぶ。木曽前岳 (2,826m)、中岳 (2,925m)、伊那前岳 (2,883m)、宝剣岳 (2,931m)
を含めて木曽駒ヶ岳と総称することもある。山体の大部分が約6500万年前の花崗閃緑岩で形成
されている。

【我が家の焚書顛末記 Ⅶ】
あとがき
この本のまえがかを書いてみないかと言われたときに、私は書ぎたレとは思わないと答え
た。でもそのあといろいろと考えてみて、やはり何か少し書いておいた方がいいかもしれな
いと思うようになった。でもまえがきではない方がいい、と私は言った。まえ、がきという
のはレささか偉そうに思えるのだ。小説にせよ、詩にせよ、自分の本にまえがきやら序文と
いったようなものを付けるのは、もっと偉い作家に(まあ五十を過ぎたくらいの人に)まか
せておくべきであろう。でもあとがきくらいなら書いてもいい、と私は言った。というよう
な経緯で、善し悪しはともかく、このような文章を書くことにあいなった。
ここに選んだ詩は、1966年から1982年にかけて書かれたものである。そのうちの
いくつかのものは『クラマス川近くで』と『冬の不眠症』と『夜になると鮭は・・・・』といっ
た詩集に収録されていたものである。それとは別に、『夜になると鮭はは・・・・』が1967
年に出版されたあとで私が書いたいくつかの詩を収録した。これらは雑誌や文芸誌に掲載さ
れたが、これまでのところ本には収録されていない。詩は発表年代順に並んではいない。そ
れら 作はだいたいにおいて、そこに含まれている思いや感覚のあり方によって、いくつか
のおおまかなグループに分けられている。感覚と感情の傾向による分類と言っていい。この
本のために詩を選び始めたときに、そのような流れが働いていることに私は気づいたのだ。
いくつかの詩は、ごく自然にしかるべきエリアか、あるいはしかるべきオブセッショソの中
に収まっていった。たとえば何らかのかたちでアルコールを扱っているものがいくつかあり、
外国旅行や歴史上の人物を扱っているものがいくつかあり、また家庭内のこと、身近な物事
だけに関係しているものがいくつかあった。そんなわけで、この本のアレンジに着手したと
きに基本的にはそういう配列でいこうと思った。例をあげると、私は1972年に『乾杯』
という詩を書いた。その十年後の1982年に、からっと違った生活のなかで、たくさんの
違った種類の詩を書いてきたあとで、私は『アルコール』という詩を書いていたわけだ。だ
からこの本のために詩を選別するときになって、その詩がどこに落ちつくべきかを教えてく
れたのは、たいていの場合には、その内容であり、オブセッション(私はテーマという言葉
を好まない)であった。そのプロセスについては特筆すべきことも、あらためて語るほどの
こともない。
もう一言だけ。かつて出版されたことのある時に関しては、ほとんどの場合わずかながら
(目には映らないくらいわずかなこともある)、改変が加えられている。しかしたとえわず
かとはいえ、改変は改変である。私は今年の夏に手を入れたのだが、それによって詩の出来
はよくなっていると思う。でも改変についてはまたあとであらためて述べる。
二つのエッセイは1981年に発表された。依頼を受けて書いたのだ。「ニューヨーク・
タイムズ・ブック・レヴュー」の担当者が私に「書くということについてなんでもいいから」
書いてくれと言ってきて、その結果『書くことについて』という短文、がでぎたのだ。もう
一つの方は『存続しつづけるものを讃えて』という「影響力」を主題とする本のために(こ
れは「アメリカソ・ポエトリー・レヴュー」のスティーヴ・バーグと、ハーバー・アンド・
ロウのテッド・ソロタロフによってまとめられた)何か書かないかという要請を受けて、「
影響力について」書かれたものである。私が寄稿したのは『ファイアズ(炎)』というもの
だった。そしてそれをこの本の題にしようと持ち出したのはノエル・ヤングである。
いちばん初期に書かれたのぱ『キャビン』で、これは1966年の作品である。もともと
は『怒りの季節』に収められていたのだが、本書に収録するためにこの夏に書き直した。
「インディアナ・レヴュー」がこの作品を1982年秋号に掲載することになっている。『
雉子』はもっとずっと最近の作品で、今月メタコム・プレスから限定出版シリーズの1つと
し押て出ることになっている。またこの秋にはニューイングランド・レヴュー」にも掲載さ
れることになっている。
私は自分の短篇をいじりまわすのが好きだ。私は書きおえた作品によく手入れをする。そ
してそのあとでもまたこつこつといじりまわす。あっちを変え、こっちを変える。何もない
ところから新しいものを書かなくてはいけないより、既に書き上げたものに細かく手入れす
るほうが好きなのだ。私にとって新しい小説を書くという作業は、なんとかそれをこなして、
そのあと小説を楽しめるように、ひとまず通過しなくてはならない難所にすぎないのではな
いかと思えるのだ。書き直しは私にとってはぜんぜん苦痛ではない。好きでやっていること
なのだ。私はぽっぽといろんなことを思いつくタイプではない。むしろじっくりと考えて注
意深く行動する性格であると思う。そのせいで書き直しが好きなのかもしれない。あるいは
そんなことぱないのかもしれない。それはただのこじつけにすぎないのかもしれない。でも
私は知っている。コ匿書き上げられた作品を書き直すことは私にとっては自然なことであり、
また私は楽しんでそれをやっているのだということを。おそらく私が書き直しを好むのは、
書き直すことによって私は自分が何を書こうとしていたのかという核心にちょっとずつ近づ
いていけるからだろう。私は自分がそれを見出せるかどうかを、ずっと心して見張っていな
くてはならないのだ。それは固定された立場というよりはむしろプロセスなのだ。
自分がこんな風にしつこく作品をいじりまわさなくてぱならないのは、性格的な欠陥によ
るものではないかという風に考えた時期も過去にはあった。でももうそんなことは思わない。
フランク・オコナしがこんなことを言っていた。自分はいつもいつも小説を書き直している
し(それも最初の段階で二十目も三十回も書き直したあとでである)、いつか書き直した作
品を収めた書き直された本を出したいものだ、と。私はここでは、ある程度それに近いこと
をする機会を与えられた。ここの中の二篇の短篇小説、『隔たり』と『足もとに流れる深い
川』(もともとは『怒りの季節』に収められたハ篇の短篇の中の二つであった)は最初に
『怒りの季節』に発表され、それから『愛について語るときに我々の語ること』に収録され
た。絶版になっていた二冊の私の本(『怒りの季節』と『夜になると鮭は・・・・』)を一つに
して再出版しないかという話がキャプラ社から来たとき、このような本を作ろうというアイ
デアが私の頭にだんだんまとまってきた。もっとも私は、キャプラ社がここに収めたいと望
んでいた前述の二篇の短篇については、いささか困ってしまった。というのは、これらはす
でに大幅に書き直されてクノップフ社の本に収められてしまっていたからである。しかし、
しばらくじっくりと考えたあとで、私はこれらの作品をキャプラ社の本に収められていたヴ
ァージョンにかなり近いかたちで収めようと決心した。でも今回は書き直しは極力控えよう
と。それらはもう一度書き直された。しかし書き直しは前回ほど大幅なものでぱなかった。
しかしいったい、いつまでこうやって書き直し続けることができるのだろうか? つまり、
これにもいつかは収穫逓減の法則が働くことになるはずではないか。でもこの二つの作品に
関しては、新しいヴァージョンの方が気に入っているといえる。新しいものの方が最近の私
の作風にもよりぴったりと調和しているのだ。
そんなわけで短篇小説についていえば、多少の差こそあれ、みんな手を入れられている。
そしてそれらは最初に雑誌掲載されたり、『怒りの季節』に収められたオリジナル・ヴァー
ジョンとはかたちを異にしている。私はこれを、旧作をより良いかたちに書き直すことがで
きるという幸福な状況に自分かいるという事実のあかしであると考えている。少なくとも、
何はともあれ、私はそれがより良いかたちであると思いたい。自分でぱとにかくそう思って
いるのだ。でも正直に言って、それが私の書いたものであれ他人の書いたものであれ、散文
であれ韻文であれ、しかるべき時間の経過のあとで手を入れたらきっともっと良くなるだろ
うなと思わないような作品にはほとんどお目にかかったことがない。このように旧作をもう
一度じっくりと見直し、手を加える機会を与えてくれた、そしてまた私の好きなようにさせ
てくれた、ノエル・ヤングに謝意を表したい。
レイモンド・カーヴァー
ニューヨーク州シラキュースにて
1982年9月7日
さて、次回のゲイリー・フィスケットジョン「君が元気でやってしてくれると嬉し」で最後となる。
【精密電流検出工学の此岸:クランプ型精密携帯電流計】
先月28日、産総研と寺田電機製作所は共同で、60アンペアまでの直流電流をクランプ型の電流
センサで精密に測定できるポータブル電流計を開発。
この記事が気になっていたのだが今日その概要を理解することに。電気機器の研究開発や電気設備
の運用では電流計測は大変重要でこの成果は大きい。例えば、電気配線への取付け・取外しが容易
なクランプ型の電流センサーが広く使用されているが、クランプ型の電流センサーは、取扱いが簡
便である反面、使用環境影響を受け誤差が生じ測定精度限界がある。特に近年、直流による給電(
直流給電)が進み、直流の電流測定の課題である。今回、新たな構造の直流電流用クランプ型セン
サーと直流電流計を開発し、測定値の誤差を自動検知・補正する機能を付加して測定精度を大幅に
向上。さらに、小型化・省電力化を図り、電池駆動のポータブルな精密電流計を実現。
今回の開発の特徴は、電流が流れると、その周囲には磁界が生じる。この磁界の大きさに応じた電
気信号を出力するホール素子を利用すれば、非接触で直流電流を測定できるが、この原理を利用し
た従来型のクランプ型直流電流センサーは、ホール素子のオフセットとその変動やセンサー部の磁
化(着磁)による誤差が生じるため、高精度測定は困難であったが、そこで、電流計のクランプ型
センサー部分に、(1)着磁を検知し消磁を自動で行う機能や(2)ホール素子出力のオフセット
とその変動を検知し補正する機能を開発付加。(3)そのために、機能部分の小型化を進め、アタ
ッシェケース(縦 406mm、 横 499 mm、 高さ 192 mm)内にコンパクトな精密電流計を実装――セ
ンサを含めた電流計全体重量は約8.2 kg――することで容易に持ち運びでき、商用コンセントが利
用できない車内や工事現場のような環境でも使えるよう内部バッテリーで最大4時間の駆動を可能と
した(上図参照)。

このポータブル精密電流計と従来型の電流計を用い、測定誤差評価を行った実験結果、上記グラフ
のような評価実験を積み上げ、最終的に開発したポータブル精密電流計の測定精度を 0.1%程度
と評価した。これは従来型と比べて約10倍の精度向上し、つまり計測電流値が低くなるほど、従
来器の誤差は大きくなるという特徴があることがわかる。

開発経緯は詳細はわからないが、寺田電機製作所の「特開2015-232489 電流測定装置」(上図)
見る限り基本的な考え方は同社にあり、技術改良(開発)に当たり、その評価方法(評価装置)は
産総研の「特開2011-226819 電流比較器」(下図)の例のように超精密な評価技術を応用したの
では――産総研の微小な磁場測定技術、例えば、超伝導量子干渉素子(Superconducting Quantum
Interference Device:SQUID)――を利用し開発したのではと考える。
※ 超伝導量子干渉素子とは、ジョセフソン接合を用いた素子(磁気センサ)であり、微小な磁場
を測定するのに使用される。「dcSQUID」「rfSQUID」の二種類があるが、 最も高い感度を備
える磁気センサとして、超伝導の状態にあるリングに外部から磁界を加えると、リングにはそ
の磁界を打ち消すように電流(遮蔽電流)が流れ、リングの一部に細い部分(ジョゼフソン接
合)を作っておくと、そこにわずかな遮蔽電流が流れただけで超伝導の状態が崩れ、常伝導の
状態となって、細い部分に電圧が生じる原理を利用したもので、わずかな磁場の変化に対応し
て電圧を取り出すことができる。

【帝國のロングマーチ 29】
● 折々の読書 『China 2049』47
秘密裏に遂行される「世界覇権100年戦略」
ニクソン政権からオバマ政権にいたるまで、米国の対中政策の中心的な立場にいた著者マイケル・
ピルズベリーが自分も今まで中国の巧みな情報戦略に騙されつづけてきたと認めたうえで、中国の
知られざる秘密戦略「1000年マラソン( The Hundred-Year Marathon )」の全貌を描いたもの。
日本に関する言及も随所にあり、これからの数十年先の世界情勢、日中関係そして、ビジネスや日
常生活を見通すうえで、職種や年齢を問わず興味をそそる内容となっている。
常生活を見通すうえで、職種や年齢を問わず興味をそそる内容となっている。
【目次】
序 章 希望的観測
第1章 中国の夢
第2章 争う国々
第3章 アプローチしたのは中国
第4章 ミスター・ホワイトとミズ・グリーン
第5章 アメリカという巨大な悪魔
第6章 中国のメッセージポリス
第7章 殺手鍋(シャショウジィエン)
第8章 資本主義者の欺瞞
第9章 2049年の中国の世界秩序
第10章 威嚇射撃
第11章 戦国としてのアメリカ
謝 辞
解 説 ピルズベリー博士の警告を日本はどう受け止めるべきか 森本敏(拓殖大学特任教授・
元防衛大臣)
第10章 威嚇射撃
百聞不如一見――百聞は一見にしかず
『漢書』趙充国伝
※ 百聞不如一見、兵難遙度、臣願馳至金城、図上方略(百聞は一見に如かず。軍事
情勢は離れたところから推測しがたいので、わたしは金城に駆けつけ、上策
を図りたい)
 Dec 03, 2012
Dec 03, 2012
2009年になっても、同僚とわたしは、中国人はアメリカ人と同じような考え方をすると
思い込んでいた。中国はアメリカや近隣諸国に対して攻撃的な態度をとりはじめたが、わたし
たちからすればそれは思いがけないことであったし、中国が主張を強める背景に、より大きな
計画があるとは思ってもみなかった。疑わしきは罰せずと、数々の疑惑を好意的に解釈したの
はわたしだけではなかった。結局、マラソン戦略に対するわたしの理解は、ゴールを急がなけ
ればならない理由はない――少なくとも今しばらくは、というものだった。偶然続いたかのよ
うな、中国が主張を強めた――連の出来事は、アメジカで論争の鮪となったが、中国のメッセ
ージには、それらの出来事をつなぐ連続的パターン、つまり戦略は存在しない、とされた,こ
れは、中国に大規模な戦略はないという従来のメッセージと一致していた。実際、アメリカに
詳しい中国きっての国際政治学者、王脚思は、フオーリン・アフェアーズ誌にこの問題に関す
る小論を絨せた(注55)。
同僚とわたしは、中国が覇権国アメリカを挑発しようとするはずはないし、中国の経済力と
軍事力がアメリカを威圧するには少なくとも20年かかる、と見ていた。これらすべてが意味す
るのは、中国は決して、近隣諸国やアメリカに攻撃的な態度をとって自滅したりはしない、と
いうことだ。だが、2014年までに、アメリカ政府当局者は連邦議会に、まさにそのような
攻撃的な主張が見られるようになった、と伝えていた。それに気づくのに、なぜこれほど長い
年月を要したのだろうか。
アメリカ情報コミュニティとわたしが、中国のより大きな意図に気づかなかった理由の一つ
は、台湾に対する中国の姿勢が和らいだことを完全に読み違えたところにある。2000年代
の胡錦濤政権以降、中国は台湾を力で脅すのをやめ、代わりに、より寛大で間接的なアプロー
チ、主に、経済的に台湾政府に影響を及ぼすという方法をとるようになった(注56)。そうす
ることで中国は、台湾の与野党、企業のリーダーマスメディア、一般大衆の問に深く入り込ん
だ。伝えられるところによれば、胡は、台湾を征服するより「買収」するほうが楽で、金がか
からない、と側近に打ち明けたそうだ(注57),中国と台湾は2009年に「両岸経済協力枠
組協定]に調印し、経済関係を正常化した。その結果、現在、中国・台湾問を週に約700便
の定期便が行き来し、2013年には280万人の中国人が台湾を訪れている。さらに、中国
政府は台湾の財界エリートを味方に引き入れ、その多くは中国・台湾間の友好回復を強く支持
するようになった。中国びいきの台湾商人が台湾の主要な新聞社とテレピ局を買収し、中国政
府はこれらのメディアや、財政援助した他のメディアに影響を及ぼしている(注58)。
2013年の秋に北京を訪れて初めて、わたしは自分たちが間違っていたこと、そして、ア
メリカの衰退に乗じて、中国が早々とのしあがりつつあることに気づいた。北京は快晴で涼し
かったが、朝の渋滞は普段よりひどかった。1週間、雨が続いた後の好天だったので、100
万人を超す住民が町から出ようとしていた。アメリカ大使館から7マイル西にあるブレジデン
シャルホテルで2日間にわたって会議が開かれ、わたしは5人の将官と60人の国防の専門家と
会う予定になっていた。遅れたくなかったので、予定より1時間早く車で出発し、天安門広場
の脇を抜け、政治局の秘密会合センターの前を通る道を選んだ。それが大きな間違いだった。
天安門前の通りには、動かない車の列が1マイル以上先まで続いていたのだ。ため息をつく
運転手に、右折して紫禁城の赤い壁沿いに進み、その後左折して近道を北に向かうよう頼んだ。
車内で、中国語での議論のための覚え書きに目を通した。議題となるのは、現代の軍事カバラ
ンスで、論客は軍部のタカ派として知られる朱成虎少将である。2005年に、アメリカが攻
撃すれば、中国には核で反撃する用意があることを明らかにして、世界的なニュースを巻き起
こした人物だ(注59)。いかにもふさわしいことに、議題の一つは将来の核でフンスと軍縮の
見通しだった。もうひとりのタカ派、彭光謙少将は、『戦略学』という古典的教科書の著者で、
力の均衡を評価する方法について述べることになっていた。また、数名の法律学教授が、南シ
ナ海に関する中国政府の主張の概要を述べるという。
この項つづく